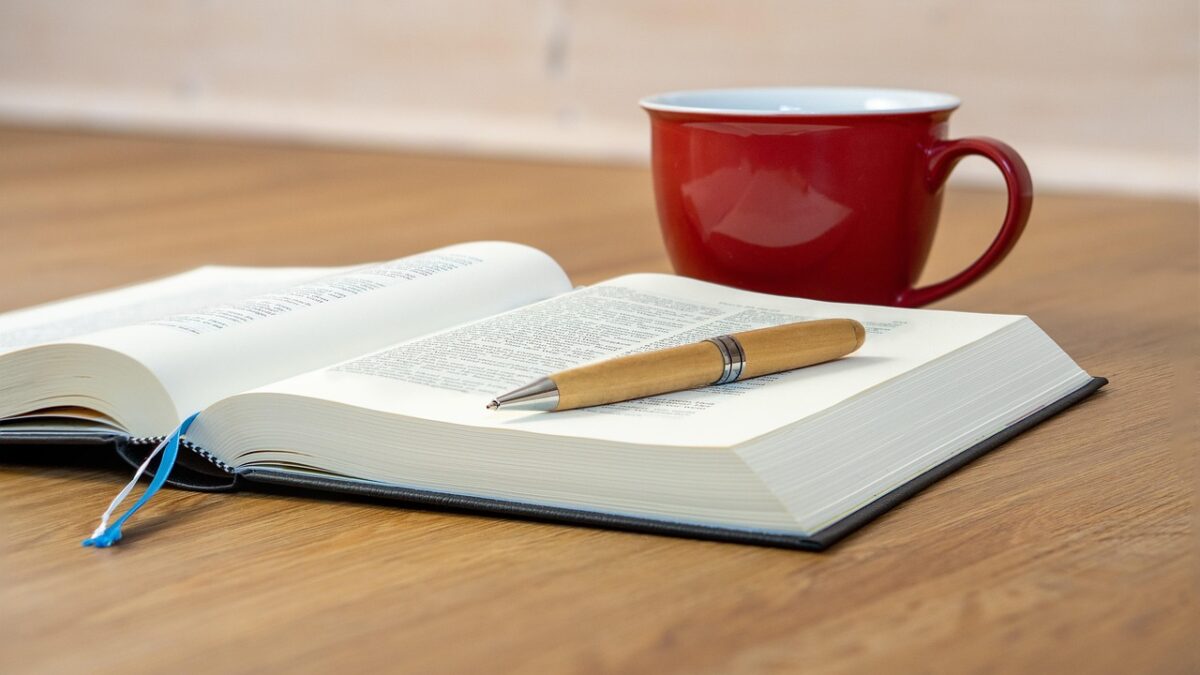こんにちは、糸です。発達障害疑いの息子を育てています。
幼少期からあれ?と思うところはあったものの、療育に通うようになったのは4歳のころでした。
発達障害についてもほとんど知らない状態で療育に通いはじめました。
療育に通ってみて思うのは「もっと早くあれこれ知っていたかった…」ということです。私がブログを始めたのは「発達障害について理解を深めたい」と思ったからです。さらにいうならば、「理解することで先の不安を解消したい」ということでした。知識って身を助けるんですよね。
というわけで、今回は発達障害、特にASDについて学ぶべく、本やネットなどからまとめてみました。
発達障害の定義 – AIより
発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達に関わる障害の総称です。主な特徴としては:
- 日本の発達障害者支援法では「自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現するもの」と定義
- 主な種類:自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(LD)、発達性協調運動障害(DCD)
- 知的障害を伴う場合と伴わない場合がある
- 生涯にわたって特性が続くが、環境調整や支援により困難さを軽減できる
- 個人差が大きく、複数の障害が併存することも多い
発達障害は「障害」ではなく「特性」として捉え、適切な支援を行うことが重要です。
今はとても便利な時代ですね。AIに聞いたらだいたいなんでも答えがすぐ返ってきます。
発達障害とは以下の4つを指すということです。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 限局性学習症(LD)
- 発達性協調運動障害(DCD)
発達障害については知的障害の有無は問わないということですね。
また、アスペルガー症候群は自閉スペクトラム症(ASD)に含まれることになったようです。診断名としては古く、今では使われないようですね。
参考サイト:https://junior.litalico.jp/about/hattatsu/aspe/
「スペクトラム」という単語は日本語で「連続体・範囲」という意味があり、特性の濃淡にグラデーションがあることを示しています。
特性について調べていると「ここはあてはまるな」「でもここは当てはまらない…」と無限ループに陥りがちなのですが、特性のグラデーションによって特性が出るところと出ないところがある、と理解ができます。
特性、というのは個性のことを指しています。それによって日常に困難が生じる状態を「発達障害」というようです。
自閉スペクトラム症(ASD)とは
発達障害のなかでも自閉スペクトラム症(ASD)について調べてみました。
精神科医の本田 秀夫先生の本がわかりやすかったです。ASDと言われたらまずこの本をサラッと読んでみるのが良いと思いました。図書館にもありました。
https://amzn.asia/d/a2HZ0xt
https://amzn.asia/d/a2HZ0xt
https://amzn.asia/d/a2HZ0xt
https://amzn.asia/d/a2HZ0xt
https://amzn.asia/d/a2HZ0xt
https://amzn.asia/d/a2HZ0xt
https://amzn.asia/d/a2HZ0xt
https://amzn.asia/d/a2HZ0xt
- 孤立型
- 受動型
- 積極奇異型
- 尊大型
うちの子エピソード
うちの子は基本的には1と2の型が該当しています。
息子は1歳くらいから同世代の子を避ける傾向がありました。自閉症の子は防衛反応で同世代を避けることがある、というのをブログで見たことがあります(URL見失いました…)
幼稚園に入った頃にはチックが出てしまい、先生からは「集団行動に参加はしているが、無理している様子が見られる」とのことでした。
チックは数ヶ月でおさまりましたが、ストレスを感じつつも言われたことはやる、という受動型のあらわれなのかなと思います。
また、周りに合わせて行動はしているものの、本当にやりたいわけではないのでストレスが溜まっている様子が見られます。
そういった生活を続けているからか、息子に「なにがやりたいの?」「やりたいことは何?」と聞くと、「わからない」と答えることもしばしば。こういった状態を過剰適応というようです。
5歳にして過剰適応できる息子に驚きます。知能の高さゆえの悩みなのかもしれません…(まだWISCなどは受けていないので想像ですが)
また、療育では先生にくっつきすぎてしまう傾向があり、療育からは積極奇異型として対応が取られている気もします。この先支援によってありのままでいられるようになったときに、積極奇異の傾向が出てしまうこともある、と先生に言われてびっくりしました。
親としてはかわいいな〜で済むことですが、大きくなってきてだんだんそれでは済まなくなってしまうのも心配です。療育に繋がれてよかったと本当に思いました。
おわりに
発達障害についての理解を深めることで、自分の子どもへの理解が深まった気がします。
どうして○○なの!?と怒るのではなく、「こういう状態だからこうしているんだな」と息子のことを理解できるようになったらいいなと思っています。